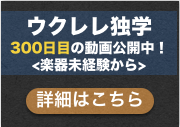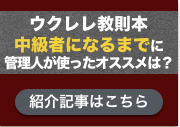今日のコラムでは、初心に帰って「ああ、こういう事があったな」という所から新しいお話をひとつさせて頂きました。情報過多だと言われて久しい昨今だからこそ、自らの体験をベースにする「一次情報」を多く手に入れる事で「自分なりに正しいと思える判断」が出来るようになる(不要な情報を捨てる事ができる)、、と私は考えます。
たとえば一般の方のサイトで、そこに「私はウクレレ中級者として日々演奏を楽しんでいます」と書いてあっても、実はその実力はピンキリです。そこを見極めるシンプルな方法は「そのサイトの運営者の実際の演奏を見る・音を聴く」事が最も手っ取り早いはずです。
なぜならウクレレの場合、TOEICのような「客観的な点数」が無く「中級者の定義」が曖昧だからです。ウクレレを購入して5年が経過しても1ヶ月に2回しか練習をしなければ、実は練習日数は、私の200日目にも届きません。
また「一次情報」の使い方は、前述のように「情報の確度を確かめる」という使い方もありますが、どちらかと言うと「自分にあった目線の情報を得る」ために使うと、より建設的だと思います。
「その視座(視点の高さ)からされている発言なのか」と言う事が理解できれば、物事の捉え方そのものが変わります。たとえば、ある発言があって、それが「これまでのウクレレ学習の常識を覆すような大胆なもの」だったとして、それが「10年の経験を持つレッスンプロが述べている事」なのか「始めたばかりの初心者の感想」なのかで、聞き手側の「捉え方」はずいぶん変わります。
情報の取捨選択において重要なのは「何を?」もそうですが「誰が」(どう言う人が)発信しているか?を見極める事も重要です。楽譜の難易度しかり(編者のクセや得意な難易度・アレンジなど)、サイトの情報しかり(サイト運営者の演奏の技量)、この視点を持って取り組むと、自分にとって有意義な展開に持って行きやすい事でしょう。
■スポンサードリンク
 Copyright secured by Digiprove © 2017
Copyright secured by Digiprove © 2017