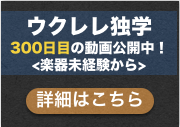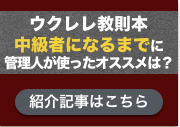ウクレレレッスン.019 ワークショップ3回を終えて学んだ(楽譜以外の)1番大事なポイント
- 2017/5/14
- 上達のヒント

受講日:2017/05/14
本日「残酷な天使のテーゼ」の全3回のワークショップが終了いたしました。詳細の譜面・テクニックや奏法などを公開するのは、道徳的に避けるものだと思っておりますので、自分の備忘録の為に「演奏に対する考え方」で最も大事だと思ったポイントを1つだけメモ的に保管しておきます。
▼ポイント
プロとアマチュアの違いは音の「抑揚」(よくよう)にある
勝誠二先生の演奏を聴いていて「ああ、これはモノに出来たらアウトプットが劇的に変わるな」と明確に感じたポイント。それが、1つの楽曲の中で頻繁に出てくる「音の強弱の変化」です。一本調子で奏で続けるのでは無く、ボリュームを小さく収めたり、あるいは大きく広げたりする事で「演奏する側」の「意志」を楽曲に乗せることが出来るという考え方です。このテクニック自体は、他の演奏にも生かすことの出来る汎用性の高いものだという理解です。
▼どうやって抑揚をつけるのか?
ウクレレは大きな音の出ない楽器であるという前提を理解する
ウクレレはどんなに全力で弾いても大きな音を出すのが苦手な楽器です。ですから「音の強弱をどのように作るのか?」に対して「弱い音を極力弱く見せる」という手法が紹介されていました。これも「なるほどな」と唸った点です。元を小さくする子どで、音量を上げた時に、絶対的な大きさが出ていなくても聴き手は「大きく聴こえる」という「相対的なインパクト」を狙ったテクニックです。
▼具体的に何をするのか?
では、具体的にはどのように「抑揚」を生み出すのでしょうか。カギはストロークにありました。ストロークする側の指を寝かせたり、立てたり、曲げて引きつけたり、ストロークする指そのものを違う指に変えて演奏したり、、、と複数の要素を変えて演奏をする事で音の強弱を調整・表現します。ここで大事なのは「小さく聴かせたいから、ゆっくり演奏する」ということはなく、あくまでも同一の強さ、テンポでのストロークに対し「奏法だけ」を変えることで、結果的に音に強弱をつける事ができるという点です。
この辺りをいかに演奏の中で表現できるか。どれだけの引き出しを持つ事ができるか?
今後の演奏に応用力をつけるという意味でも(3回目のワークショップでは細かい譜面のアレンジもありましたが)特に重要で、かつ他にも応用が利く技術として「最重要・学習ポイント」としておこうと思います。
総括:やっぱりワークショップは学ぶ事が多いなあと思いました(笑)
■スポンサードリンク
 Copyright secured by Digiprove © 2017
Copyright secured by Digiprove © 2017